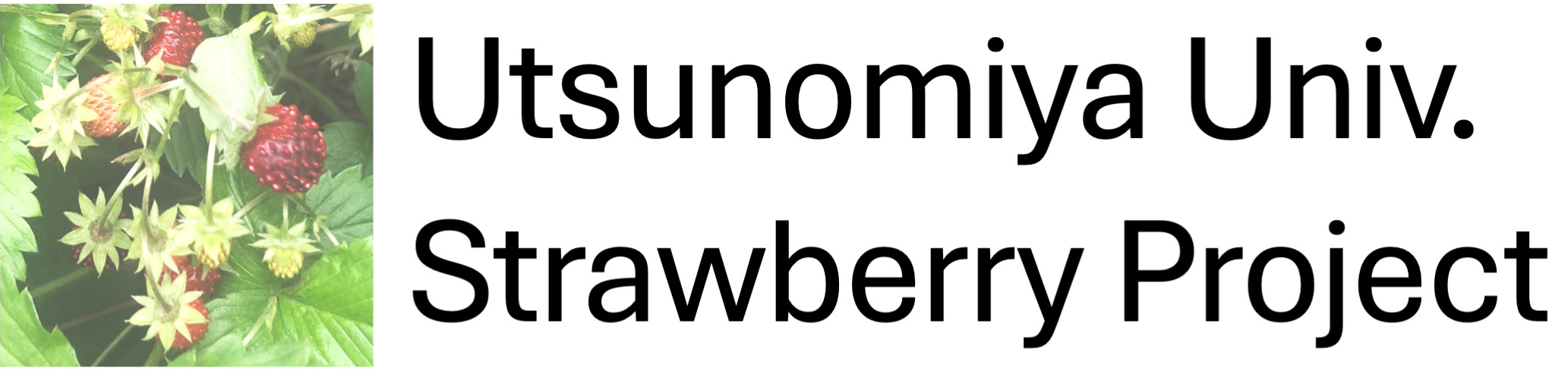コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動イチゴに関連する学術論文の紹介
- 【炭疽病】野生イチゴ の遺伝的多様性は栽培イチゴの炭疽病抵抗性育種に有望です。ドイツ由来の72系統の 野生イチゴF. vescaを用いて炭疽病菌C. nymphaeaeの抵抗性を解析した結果、単一から複数の病原株に抵抗を示す系統が見られました。少なくとも6株の病原株に抵抗性を示したF. vescaの系統(NO 04 002)では、栽培イチゴで知られる抵抗性遺伝子 RCA2 が検出されず、基本的防御機構による抵抗性が示唆されました(Rose et al., 2005, Plant Biol.)。論文はこちら>> https://doi.org/10.1111/plb.70087
- 【系統進化】栽培イチゴ(Fragaria × ananassa)は、8倍体の野生イチゴ種同士の交雑により誕生したことが知られています。中国の研究グループは、これら8倍体野生イチゴの進化史を解明するためゲノム解析を行いました。その結果、F. viridis、F. nipponica、F. nilgerrensis、F. iinumaeなどの現存種に加え、近縁の絶滅または未発見の二倍体種が関与し、交雑を経て約80万年前に8倍体野生イチゴが成立したことを明らかにしました。論文はこちら>> Fan et al 2025 PNAS https://doi.org/10.1073/pnas.2502814122
- 【土壌】中国では、イチゴの連作障害が深刻化しており、その要因の一つとして、根から分泌されるフェノール酸類が土壌に蓄積することによる微生物バランスの崩壊が挙げられます。これらの変化は、生育阻害や収量・品質の低下を引き起こす原因となります。耐性リスクがなく、安全で環境負荷の少ない対策の確立が強く求められています。(Xie et al. 2021)。 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125102044
- 【インフォマティクス】Jin et al. (2025) Genome Biol. は、栽培イチゴ F. × ananassa “EA78” のセントロメアに存在するリピート配列が、同一サブゲノム内のホモログ間では高い類似性を示す一方で、異なるサブゲノムのホメオログ間では多様化していることを明らかにしました。本研究は、8倍体イチゴにおける染色体分配の安定性の理解に重要な貢献をしています。https://link.springer.com/article/10.1186/s13059-025-03482-0
- 【免疫】イチゴと病原体の相互作用に関する研究では、角斑病菌Xanthomonas fragariae がタンパク質XopKをイチゴに送り込むことによって、イチゴのアブシジン酸の蓄積およびそのシグナル伝達を抑制することが明らかにされています。この抑制により、気孔閉鎖が阻害され、病原菌が侵入する可能性が示唆されています(Cai et al 2025 Plant Physiol Biochem)。 https://sciencedirect.com/science/article/pii/S0981942824010362
- 【化学】野生イチゴ22系統から揮発性化合物VOCsを特定した研究(Xu et al 2025 Food Chem X)によると、F. nilgerrensisやF. mandshuricaでは、VOCs量とそれに対するラクトン類の寄与が高く、強い香りの要因になることを示しました。優れた香り特性を持つ遺伝資源は育種やジャム製造、香料抽出に期待されます。 https://sciencedirect.com/science/article/pii/S2590157524009805
- 【ストレス応答】イチゴ果実の赤色の色素成分であるアントシアニン。アントシアニンは低温ストレス下で蓄積され、紫外線や可視光を吸収して植物内部の温度を調整し、細胞膜の安定化にも寄与します。シロイヌナズナではCBF/DREB1経路を通じてROS(活性酸素種)除去と、耐寒性向上に関与します(Li et al 2016 Plant J)
- 【ストレス応答】野生イチゴF. vescaの低温耐性を向上させるDREB1B遺伝子の研究(Luo et al., 2024, Plant Cell Environ)では、冷涼な気候を好む日本固有種F. nipponicaや、中国北部に自生するF. mandschuricaにおいて、他の野生種と比較してDREB1Bの発現が高いことが確認されています。
- 【ストレス応答】Luo et al 2024, Plant Cell Environ の研究によると、野生イチゴF. vescaにおけるDREB1B遺伝子は、SCL23およびCHSの発現を直接制御し、耐寒性にも関与することで知られるDELLAの安定化とアントシアニン蓄積をそれぞれ促進することで低温耐性を強化することが示されています。
- 【遺伝子工学】Kim et al 2025( J Amer Soc Hort Sci) は、栽培イチゴ2品種を用い、高いシュート再生率を示す最適な組織培養条件に加え、アグロバクテリウム媒介によるCRISPR/Cas9法で高効率な遺伝子編集を達成する条件の最適化を行いました。イチゴの機能研究のさらなる進展が期待されます。https://doi.org/10.21273/JASHS05388-24
- 【遺伝子工学】スペインの研究グループは、CRISPR/Cas9法でイチゴ品種「チャンドラー」のFaPG1遺伝子をノックアウトすることで、果実の硬さと貯蔵性が改善することを示しました。本研究は、栽培イチゴにおけるゲノム編集が農業形質の改変に繋がった初めての例です(López-Casado et al 2023 Hortic Res)
- 【遺伝子工学】高倍数性作物のゲノム編集は難易度が高いですが、8倍体の栽培イチゴでは2019年以降、内因性のマーカー遺伝子や花の発達に関与するMADS-box TM6遺伝子、さらにアントシアニン結合酵素をコードするRAP遺伝子の編集が、イギリス、スペイン、中国の研究グループによって成功しています(Wilson et al 2019 Plant Methods, Martín-Pizarro et al 2019 J Exp Bot., Gao et al 2020 Plant Biotechnol J.)
- 【遺伝学】Fragaria属における性決定の新発見。四倍体野生イチゴ Fragaria moupinensis において、W染色体特異的な雌性決定遺伝子 FmoAFT を特定しました。本研究により、四倍体および八倍体イチゴの雌雄異株性が独立に進化した可能性が示唆されました。さらに、栽培イチゴにおいても FmoAFT が雌性機能に関与することを確認しました。本成果は、性決定機構を活用したイチゴ育種への応用に貢献するものです(Qiao et al. 2024 Plant Biotech J)。
- 【免疫】栽培イチゴ(Fragaria x ananassa, Duch)から、イチゴ灰色かび病などの真菌感染症の防除や成長促進に有益な細菌が分離されました。これらの菌株は、オーキシンやジベレリンなどの植物ホルモンを生成し、防御反応にも関与しています(Hirsch et al 2024 Plant Growth Regul)。微生物の力を利用した作物の栽培技術の発展が期待されます。https://link.springer.com/article/10.1007/s10725-023-00989-z
- 【農研機構】ドローンを活用するイチゴの生育観測手法を開発 -生長点の時系列観測により生育診断を高度化- https://researchmap.jp/press_releases/press_releases/view/633014/d25c90bcfd8f1c1fc45c9a7bf9032908?frame_id=1601185
- 【栽培】イチゴに限らず果菜類の栽培で受粉は重要ですが、ミツバチなどの花粉媒介昆虫の減少や人工受粉のコストが問題です。 2020年には、花粉を混ぜたシャボン玉をドローンから飛ばして受粉させるユニークな方法が発表されています。イチゴで利用する日は来るでしょうか? https://sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004220303734
- 【栽培】イチゴでは、開花時期や温度などの生育条件が異なる品種を交配して新品種を作出する際に、花粉の保存が必要になります。花粉の発芽率を低下させないよう、最適な保存条件や発芽を誘導する培地条件の検討が行われています(Yamaguchi et al 2024 The Horticulture Journal)https://jstage.jst.go.jp/article/hortj/advpub/0/advpub_QH-097/_pdf
- 【分類】ヤブヘビイチゴ (Potentilla indica) は、同属のヘビイチゴや Fragaria 属の野生イチゴが2倍体(染色体数2n=14)であるのに対し、12倍体(染色体数2n=84)であることが確認されています。Naruhashi & Iwatsubo (1991) による Cytologia での報告では、ヤブヘビイチゴの非常に美しい染色体標本が紹介されています。https://jstage.jst.go.jp/article/cytologia1929/56/1/56_1_143/_pdf
- 【ストレス応答】野生イチゴF. vescaでは、成長や環境ストレスに応答するエピジェネティックな変化の世代間遺伝が報告されました 。クローン繁殖するイチゴは、DNA配列に依存しないメチル化変異の遺伝により環境適応が可能になるのかもしれません(Sammarco et al 2024 New Phytol)。
- 【分類】Potentilleae亜科に属する13属の系統関係について、Li et al. (2024) による研究が発表されました。Potentilleaeは、バラ科の16族の中で最大の群を成し、約1700種を含む13属から構成されています (Li et al. 2024, Mol. Phylogenet. Evol.)。
- 【細胞】本プロジェクト代表の児玉豊教授の研究グループより、野生イチゴF. vescaの葉緑体光定位運動に関する論文が発表されました。本件究成果はイチゴの光合成効率と生産性を向上させるための重要な一歩となり、イチゴ栽培の条件改善に寄与することが期待されます。https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15592324.2024.2342744
- 【栽培】中日性(day neutral)品種のイチゴAlbionを用いた研究によると、遠赤外線と青色LEDを1:5の比率で組み合わせた光を苗に暴露することで、花芽誘導と花の発達を改善し果実生産を増加させる可能性が示されました。https://doi.org/10.1139/cjps-2021-0081
- 【アレルギー】イチゴの主要アレルゲンであるFra a 1のアイソフォームの中でも、特にヒトIgEと強く結合することが示されているのがFra a 1.01です。Fra a 1.01タンパク質は、低温ストレスなどの環境要因に応答して蓄積することが示唆されています(Ishibashi et al., 2019, Hort. J)。
- 【ストレス応答】栽培イチゴから単離されたサーチュイン遺伝子の一つであるFaSRT1-2は、果実において過剰発現させると熟成が促進され、アントシアニンや糖類の含量が増加することが示されています。また、FaSRT1-2は高温ストレスや感染症に対する耐性の調節にも重要な役割を果たすことが明らかになっています(Wang et al., 2024, PL CELL ENV)。
- 【生態】栽培中の野生イチゴ Fragaria iinumae について、同じFragaria属でも、F. nipponica、F. nubicola、F. viridis は自家不和合性を示すのに対し、F. iinumae、F. vesca、F. nilgerrensis は自家和合性を示します。自家不和合性は、Fragaria 属内で独立して獲得された特性であると考えられています(Chen et al 2023 Plant Diversity)https://sciencedirect.com/science/article/pii/S2468265922000415?via%3Dihub
- 【果実品質】白いイチゴはその魅力的な外観に対して、収穫後の熟成や貯蔵期間が短いという問題があります。白いイチゴ品種Snow Princessを用いた実験によると、果実を硫化水素ナトリウム(NaHS)で処理することにより、活性酸素種やエチレン生成が抑制され、収穫後の鮮度が長持ちする効果があることが示唆されています(Sun et al., 2023)。https://sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521423002971
- 【遺伝】野生イチゴ F. vesca の葉に関する研究では、葉のギザギザが形成される際や小葉に分かれる際に、同じ遺伝子 cuc2a が働くことが確認されていますが、それぞれの過程を制御している上流の遺伝子は異なることが示唆されています(Luo et al 2024 Current Biology )。https://sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960982224000101?via%3Dihub
- 【インフォマティクス】Fragaria属で初めて全ゲノムが解読されたのはエゾヘビイチゴ(F. vesca)であり、その全ゲノムデノボアセンブリに日本の品種である麗紅が用いられました。この研究は、Hirakawa et al. により2014年に『DNA Research』誌に発表されています。https://academic.oup.com/dnaresearch/article/21/2/169/404005
- 【生態】追熟型果実(例:リンゴやモモなど)は地上を徘徊する動物によって、非追熟型果実(例:イチゴやブルーベリーなど)は樹上性の動物、特に鳥やコウモリによって種子が散布される傾向があります。果実が追熟型であるか否かの違いは、種子散布者に対する適応進化の結果として生じた可能性が考えられます。https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2021.0352
- 【育種】ピンク色の花つける鑑賞用のイチゴ品種「ピンクパンダ」。ピンクパンダを種子親(雌)にもち、ピンク色の花と白い果実をつける新しい品種G23が2023年に発表されました Guan et al 2023 HortScience https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/58/9/article-p1005.xml#container-10126-item-10143
- 【病害】イチゴの根圏微生物(根の周囲に生息する微生物)が、土壌媒介病原体に対する抵抗性において重要な役割を果たしている事例が報告されています。植物体と共生する微生物との関係には、イチゴ栽培に役立つヒントが含まれている可能性があります( Lazcano et al 2021 Sci Rep) https://www.nature.com/articles/s41598-021-82768-2#Sec1
- 【遺伝子工学】野生イチゴ F. vesca では、転写因子 FvWRKY50 が栄養および生殖成長を制御していることが示されています。この遺伝子のノックアウトにより、開花時期の早期化と葉の老化が促進されることが確認されました。 https://doi.org/10.1093/hr/uhad115。
- 【分類】ヒメヘビイチゴの葉緑体ゲノムを解読した結果、形態的な特徴に反して、その系統的位置はキジムシロ属の中でもコアグループから離れていることが明らかになりました。 Park et al 2019 Mitochondrial DNA Part B
- 【病害・AI】病気に感染したイチゴの葉と非感染の葉の画像をAIに学習させることにより、うどんこ病を検出する技術が開発されています(Shin et al 2021 Comput Electron Agric)。
- 【病害】近年、イチゴを悩ます炭疽病に対する殺菌剤耐性の問題が浮上しています。殺菌剤が標的とする病原菌のタンパク質構造が変化することにより、薬剤の結合力と効果に影響を及ぼす分子メカニズムが明らかになりつつあります(Cortaga et al 2023 Phytoparasitica)。
- 【化学】これまで廃棄されていた野生イチゴの葉について、LC-MSを用いて成分を詳細に分析した結果、高い抗酸化作用が期待できることが示されました(D’Urso et al J Pharm Biomed Anal 2018)
- 【害虫】ハダニの抵抗性を高める要素に注目した研究において、イチゴの葉表面における非腺性トライコーム(毛状突起)と腺毛の密度が高いほど、ハダニの移動距離が短縮し、卵の着床および孵化数が減少することが明らかにされています(Agric Sci 2020)。https://doi.org/10.1590/1413-7054202044006920
- 【インフォマティクス】イチゴの研究は世界中で活発に行われていますが、食用イチゴの全ゲノム解析に世界で初めて成功したのは日本の かずさDNA研究所です(Hiakawa et al 2013 DNA Research)。 https://doi.org/10.1093/dnares/dst049」
- 【遺伝子工学】野生イチゴF. vescaでは、転写因子FvebZIPs1.1に変異を導入することで、イチゴの甘味(糖の含有量)を増加させることに成功しています( Xing et al 2020 Genome Biol)
- 【化学】一般的に栽培されているイチゴ、Fragaria ananassa は350種以上の揮発性化合物を含んでおり、そのうち19種類がイチゴの香りに強い影響を与えることが示されています。香りに関与する主要な遺伝子領域は50箇所に及びます(Rey-Serra et al 2022)。
- 【遺伝子工学】バラ科植物の中で、ゲノム編集技術(CRISPR法)によって導入された変異が次世代に継承されることが初めて確認されたのは、野生イチゴFragaria vesca です(Zhou et al. 2018, Plant Biotechnol J)。野生イチゴを利用した遺伝学の発展が今後さらに期待されます。
- 【植物ホルモン】トマトやバナナの成熟は、植物ホルモンであるエチレンによって促進されます。一方、イチゴの成熟はエチレンではなく、アブシジン酸によって促進されることが明らかにされています(Jia et al., 2011; Guo et al., 2018)。植物の成熟過程はそれぞれ異なることが示されています。
- 【栽培】カリフォルニアでは、オゾン濃度の上昇がイチゴを含む作物の収量低下につながる可能性が示唆されています(Hong et al 2020)。 doi: 10.1038/s43016-020-0043-8
- 【遺伝学】四つの祖先種を起源とする栽培イチゴにおいて、すべての遺伝子が均等に機能しているわけではなく、特定の一つの祖先種に由来する遺伝子が顕性(優性)として働いていることが示唆されています(Edger et al 2019 )。doi:10.1038/s41588-019-0356-4